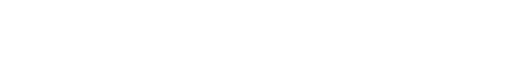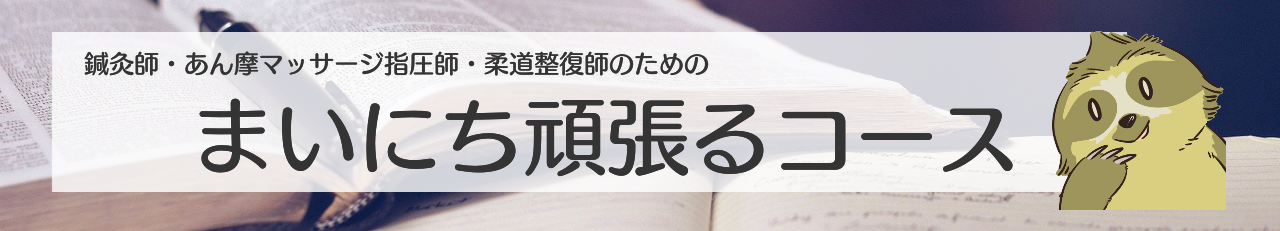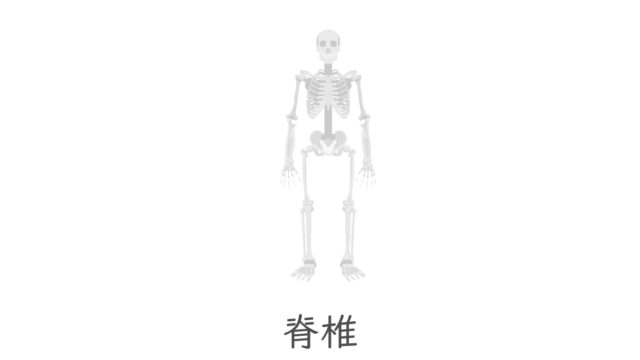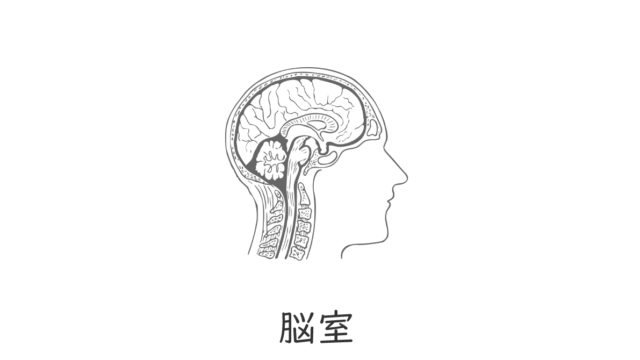脾臓について学ぶ
今回は脾臓の構造とホルモンについて学習をしていきます。
膵臓からはインスリンやグルカゴンなど血糖値に関わるホルモンが分泌していますよね。
では、そのホルモンはどの細胞からでているかご存知でしょうか。
では次の項目から本題に入ります。
【解剖学】膵臓について
膵臓は長さ約15cm、重さ70g程度の舌状の実質性臓器で、第1・第2腰椎の前を後腹壁に付着して横走する。
まずは解剖学的に膵臓を説明していきます。
第1・2腰椎あたりにある膵臓は右側から膵頭部・膵体部・膵尾部というふうに分かれています。
よく選択肢で見かけるのは「十二指腸に抱きかかえられるようにあるのは膵尾部である。」といった問題です。
この選択肢は誤りで正解は、十二指腸側にあるのは膵頭部、脾臓側にあるのが膵尾部です。
膵臓は外分泌腺と内分泌腺を持ちます。
外分泌腺は腺房とよばれ、分泌細胞が一列に並んで腺腔を球状に取り囲んでいます。
外分泌腺は膵臓のあちこちに分泌しています。
内分泌腺は、ランゲルハンス島に存在しており、α細胞・β細胞・δ細胞の3つに大別されています。
ランゲルハンス島は膵臓全体の約2%に過ぎません。
よく出題されるのは、この全体の2%しかないランゲルハンス島がどこに集中しているかです。
ランゲルハンス島は主に膵尾部に存在しています。
これが膵体部や膵尾部になっていたら誤りです。
膵頭部・膵体部・膵尾部に分かれる
膵頭部は十二指腸側
膵尾部は脾臓側
内分泌腺はランゲルハンス島
ランゲルハンス島はα・β・δ細胞に分かれる
ランゲルハンス島は膵尾部に集中している
【生理学】膵臓のホルモンについて
膵臓から出ているホルモンを以下にまとめています。
α:グルカゴン
β:インスリン
δ:ソマトスタチン
インスリンが出る細胞とグルカゴンが出る細胞そしてソマトスタチンが出る細胞はそれぞれ異なります。
α(アルファ)細胞はA細胞とも呼ばれ「グルカゴン」を分泌します。β(ベータ)細胞B細胞とも言われ「インスリン」を分泌します。δ(デルタ)細胞はD細胞とも呼ばれ「ソマトスタチン」を分泌します。
C細胞はないので注意です。
また、選択肢でよく見かけるのは「α細胞からインスリンが分泌される」という選択肢、これは誤りで正解は「α細胞からグルカゴンが分泌される」です。
なれてきたら当たり前に思えますが、ここらへん初めて聞く人はどっちがα?β?ってなると思います。
なので簡単にゴロ(覚え方)をお伝えしておきます。
ぐるっとグルカゴン
αを書くときペンを一周ぐるっとまわしますよね。なのでグルっと回すとグルカゴンをかけています。
では次項で順番にホルモンについての説明をしていきます。
グルカゴン
グルカゴンは主に血糖値を上昇させる働きを持ちます。
肝臓:グリコーゲンからグルコースへ分解促進⤴
糖新生の促進⤴
血糖値上昇⤴
血中遊離脂肪酸増加⤴
グルカゴンは血中の血糖値の低下によって分泌が促進されます。肝臓ではグリコーゲンからグルコースにして血中に放出したり、脂肪を分解し、血中遊離脂肪酸を増加させたりする働きがあります。
糖新生について
超新星ではないですよ(どうでもいいですね。)
糖新生とは、タンパク質や脂肪を分解して糖に変える働きです。
国家試験でよく出題される糖新生で使われる主な物質は以下の4つです
乳酸
ピルビン酸
アミノ酸
グリセロール
糖新生は乳をアピール
乳(乳酸)をア(アミノ酸)ピ(ピルビン酸)ール(グリセロール)
この4つ以外にも出てくるんですが、基本的な考えは糖以外の物質を糖に変えるというものなので糖が選択肢に出てきたら誤りです。
インスリン
インスリンはペプチドホルモンで21このアミノ酸からなるA鎖と30個のアミノ酸からなるB鎖よりなる。
インスリンは主に骨格筋・脂肪組織・肝臓に作用して血糖値を下げる働きを持つホルモンです。
グルコースをグリコーゲンへ変換
タンパク質の合成の促進
グルコースを脂肪へ変換
血糖値の低下⤵
インスリンのメインの働きは血糖値の低下です。
この血糖値低下のために、血中のグルコースを細胞に取り込んだり、脂肪へ変換したりして血糖値を下げていきます。
インスリンの分泌調節について
インスリンの分泌は血糖値の変動に寄って直接的に調整されています。
一部は迷走神経により分泌を促進させます。
ソマトスタチン
ソマトスタチンは膵臓のランゲルハンス島に作用し、インスリンとグルカゴンの分泌を抑制させます。
インスリンの分泌抑制⤵
グルカゴンの分泌抑制⤵
血糖値の調整について
血中のグルコースの濃度は約70~110ml/dlに維持されている。
血糖値が正常レベルより上昇するとインスリン分泌が増して血糖値を正常レベルに戻す。
一方、血糖値レベルが正常レベルより低下する、グルカゴンの分泌が増して血糖値を正常レベルに戻す。
血糖値は常にある一定の濃度を保っています。よく出題されるのは、血糖値を上げるホルモンと血糖値を下げるホルモンを選ぶ問題です。
グルカゴン
カテコールアミン
成長ホルモン
副腎皮質ホルモン
甲状腺ホルモン
インスリン
上記のように血糖値を上げるホルモンは多数存在しますが、血糖値を下げるホルモンは1つしかありません。
生物は血糖値を下げるよりも上げるほうが重要なためこのようなバランスになっていると考えられます。
血糖値を下げるホルモンが「インスリン」しかないため、インスリンの分泌低下や感受性低下によって糖尿病になってしまいます。
膵臓のホルモンまとめ

膵臓からは3つのホルモンが出ておりそれぞれ、血糖値を上げるホルモン・血糖値を下げるホルモン・それを調節するホルモンの3つです。
血糖値は上げる働きのほうが、生命維持に欠かせないので様々なホルモンが調節を担っていますが、血糖値を下げるホルモンはインスリンの1つだけです。
国家試験でもインスリンもしくは糖尿病の問題はかなり出題されますのでしっかりとマスターしていただければと思います。
最後までお読みいただきありがとうございます。
【森元塾】国家試験対策オンライン塾ではラインで答えのやり取りを行いながら、わからないところも聞くことができます。
無料ではとても言えないきわどい覚え方や資料を使って過去問やオリジナル問題を解説しています。